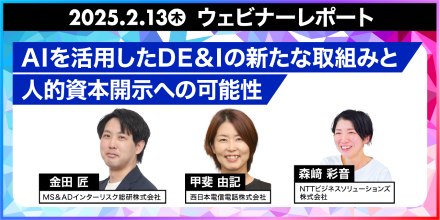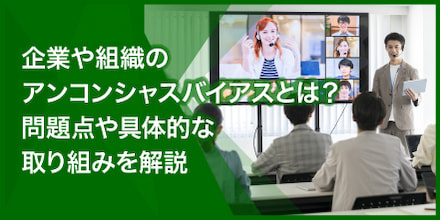ICTで経営課題の解決に役立つコラムを掲載
アンコンシャスバイアスのトレーニングとは?研修の目的・メリットやポイントを解説

アンコンシャスバイアスのトレーニングとは、アンコンシャスバイアスが職場にもたらす悪影響を軽減し、多様な従業員が働きやすい職場環境を実現するための取り組みです。しかし、具体的にどのようなトレーニングを行うべきか、分かりづらい点もあるでしょう。そこで本記事では、アンコンシャスバイアスのトレーニングの目的や方法について解説します。
アンコンシャスバイアスのトレーニングを行う目的
アンコンシャスバイアスのトレーニングを行う目的として、次のようなものが挙げられます。
- 自身が持つバイアスへの「気づき」を与えるため
- 誰もが働きやすい職場環境を整備するため
- 従業員に柔軟な視点を身に付けてもらうため
自身が持つ バイアスへの「気づき」を与えるため
そもそも「アンコンシャスバイアス」とは、無意識下で生じる偏見や思い込みを意味します。アンコンシャスバイアスは誰にでも起こり得るもので、それ自体が必ずしも悪いものではありません。しかし、職場環境や周囲の人々に悪影響を及ぼす場合、アンコンシャスバイアスは大きな問題となります。
例えば、年齢・性別・性的指向などに関するアンコンシャスバイアスが蔓延していれば、職場でハラスメントが常態化してしまうでしょう。アンコンシャスバイアスのトレーニングを行うことで、従業員が自身のもつ無意識の偏見や思い込みに気づき、組織の人間関係や業務への悪影響を防ぎやすくなります。
誰もが働きやすい職場環境を整備するため
アンコンシャスバイアスの存在により、固定観念や偏見の影響が強くなり、一部の人が働きづらさを感じることがあります。また、そうした偏見や思い込みの多い職場では、必然的に意見・アイデアを表明しづらくなるため、心理的安全性の低下にもつながります。
アンコンシャスバイアスのトレーニングを行うことで、多様な価値観や働き方を尊重する組織風土が根付き、あらゆる人が働きやすい職場環境を構築できるのです。
従業員に柔軟な視点を身に付けてもらうため
現在は「VUCA時代」、つまり先行き不透明で将来を予測しづらい状況なので、柔軟な対応が求められることが増えています。旧態依然とした組織文化や考え方では、激動のビジネス環境の変化に適応できず、大切なチャンスを逃してしまうでしょう。
アンコンシャスバイアスのトレーニングは、いわば既存の常識や固定観念にとらわれない思考法を身に付けることであり、その柔軟な視点はビジネスにも役立ちます。
アンコンシャスバイアスのトレーニングが注目される背景
アンコンシャスバイアスのトレーニングが注目されるようになった背景として、次のようなものが挙げられます。
- ハラスメントが問題視されている
- 働き方が多様化している
- DE&Iが推進されるようになった
ハラスメントが問題視されている
近年では、職場のハラスメントが問題視されることが増えています。厚生労働省が発表した「職場のハラスメントに関する実態調査について」(令和5年度)によると、過去3年間でハラスメントの相談件数は以下の通りでした。
| パワハラ | 64.2% |
|---|---|
| セクハラ | 39.5% |
| 妊娠・出産・育児休業等ハラスメント | 10.2% |
| 介護休業等ハラスメント | 3.9% |
パワハラやセクハラが特に多いですが、そのなかには悪意のないものも少なくありません。本人にはハラスメントのつもりがなくても、相手の感じ方も同じとは限らないのです。アンコンシャスバイアスのトレーニングにより、他人を思いやる習慣が身に付き、職場のハラスメントを防ぎやすくなります。
働き方が多様化している
特に2020年頃からの新型コロナウィルス流行以降、「テレワーク」「フレックスタイム制」「短時間勤務制度」など、働き方の多様化が進んでいます。また、従来の職場では「少数派」とされていた人々の社会進出も進み、企業や自治体には柔軟で寛容な職場環境づくりが求められています。
さらに重要なポイントが、「ワークライフバランス」や「働きやすさ」を求める労働者が増えたことや、さまざまな業界で人手不足が深刻化していることです。つまり、人材の確保が企業の喫緊の課題となっているのです。
しかし、組織の価値観や制度が旧態依然としたものでは、こうした時代の流れに対応できず人材確保が困難になります。職場の偏見や思い込みを改善し、多様な人材が活躍できる環境を構築するために、アンコンシャスバイアスのトレーニングが欠かせません。
DE&Iが推進されるようになった
「DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)」への注目が高まっていることも、アンコンシャスバイアスのトレーニングが重視されている理由です。DE&Iは、多様性・公平性・包摂性を企業経営に取り入れる概念で、多様な個人が能力を発揮できる環境づくりが目的です。
しかしこのDE&Iを推進するうえで、アンコンシャスバイアスが大きな障壁となります。アンコンシャスバイアスのトレーニングで従業員に「気づき」を得てもらうことで、互いを尊重し合える組織風土を醸成しやすくなります。
アンコンシャスバイアス解消のトレーニング内容

アンコンシャスバイアス解消のためのトレーニングや研修プログラムは、主に以下のような内容から構成されています。
- アンコンシャスバイアスの基本知識を身に付ける
- 自他のアンコンシャスバイアスを意識する
- アンコンシャスバイアスに対応する方法を学ぶ
- 組織・チームとして守るべきことを理解する
アンコンシャスバイアスの基本知識を身に付ける
まずはアンコンシャスバイアスの基本知識を身に付けます。アンコンシャスバイアスには、正常性バイアス(異常な状況を正常と見なす)、確証バイアス(自分の考えに合う情報だけを集める)、ステレオタイプバイアス(特定の集団に対する固定観念)などの種類があります。これらのバイアスが組織内に影響を与えるメカニズムを学ぶことが重要です。
アンコンシャスバイアスは無意識下の心理であるため、自身のバイアスには気付きにくいものです。アンコンシャスバイアスの意味や種類を知ることで、自身の思考パターンを把握できるようになります。
自他のアンコンシャスバイアスを認識する
アンコンシャスバイアスのトレーニングでは、これまでの固定観念や常識に対し、「本当にそうだろうか」「他の考え方はないだろうか」と疑問を投げかけるマインドを醸成します。例えば、「女性はこうあるべき」のような偏見や「この業務はこう進めるべき」といった固定観念は、これまでの人生で積み重ねた経験により形成されたものです。
自身の思考パターンや固定観念を意識することで、こうしたバイアスへの気づきが得られます。また、日頃から他人の発言に意識を配ることで、人それぞれ物事の見方や考え方が異なることも分かります。従業員同士でディスカッションやフィードバックを行えば、アンコンシャスバイアスへの理解がさらに深まるでしょう。
アンコンシャスバイアスに対応する方法を学ぶ
ある物事について判断を行うときは、状況や背景を冷静に認識することが大切です。例えば、自社の売上高が1割減少したとき、数値だけを見れば「深刻だ」と感じるかもしれません。ところが、業界全体で3割減少している場合は、相対的に自社の成果は優れていると判断できるでしょう。
これはDE&Iが目指す「多様性」とは関連性が浅いように思えるかもしれませんが、そもそもアンコンシャスバイアスは「視野の狭さ」から生じるものです。より広い視野で状況を判断する方法を学ぶことで、日頃から柔軟な対応ができるようになります。多角的な視野を身に付けることは、新たな価値やイノベーションの創出にも役立ちます。
組織・チームとして守るべきことを理解する
組織では往々にして「集団心理」、つまり組織のメンバーで形成される思考や感情などが発生します。集団心理が発生した組織では、論理的な思考ではなく「多数派への同調」が進み、極端な言動を引き起こす傾向があります。つまり、組織の意思決定において、多数派の意見が優勢になると、偏見や思い込みに基づく判断がなされやすくなるのです。
アンコンシャスバイアスのトレーニングでは、組織が誤った方向に進まないようにするためのポイントも学びます。例えば、多数派が形成されている状況であっても、各々が「自分事」として論理的に考え、反対意見が出た場合は冷静に受け止めるなどです。これによりメンバーが安心して意見やアイデアを表明し、組織を正しい方向に歩ませられる風土が整います。
アンコンシャスバイアスのトレーニングを実施するポイント
アンコンシャスバイアスのトレーニングを実施する際は、次のようなポイントを意識しましょう。
- 自社の抱える課題を明確化する
- 経営層や人事部にも必ず実施する
- アウトプットの機会を研修で設ける
自社の抱える課題を明確化する
アンコンシャスバイアスが自社のビジネスにどのような悪影響を及ぼしているか、まずは現状を適切に把握することが大切です。例えば、「ハラスメントが常態化している」「人事評価に偏りがある」などの場合は、アンコンシャスバイアスのトレーニングが必須だといえるでしょう。
ただし、アンコンシャスバイアスの種類は多様なので、一度のトレーニングですべてを解消するのは困難です。そこで、まずはトレーニングの種類を絞り込み、自社の最重要課題を解決するほうが効果的です。
経営層や人事部にも必ず実施する
アンコンシャスバイアスのトレーニングは、必ず経営層や人事部にも実施しましょう。企業のトップ層がアンコンシャスバイアスを理解し、自らの偏見や思い込みへの「気づき」を得られなければ、組織全体に柔軟な思考を浸透させることはできません。
実際に新任の管理職に実施する研修カリキュラムとして、アンコンシャスバイアスのトレーニングを組み込むケースが増えています。
アウトプットの機会を研修で設ける
アンコンシャスバイアスは自身で自覚しづらいため、知識のインプットだけではなく、アウトプットの機会も設けたトレーニングを行うことが理想的です。例えば対話型の研修を行うことで、他者のフィードバックを交えて自身のアンコンシャスバイアスへの気づきが得られるため、アンコンシャスバイアスへの理解がさらに深まります。
AIとの対話を通じて自身のバイアスパターンを見える化でき、意識改革や行動変容につなげられるトレーニングツールもあるため、ぜひ導入を検討してみましょう。
アンコンシャスバイアストレーニングには「karafuru AI(カラフルAI)」がおすすめ!

アンコンシャスバイアスのトレーニングを行うことで、従業員に自身の偏見や思い込みへの「気づき」を与え、誰もが働きやすい職場環境を整備しやすくなります。
ただし、組織のアンコンシャスバイアスと向き合うためには、経営層や人事部も含めたすべての従業員に対し、対話型のトレーニングを行うことが大切です。教育だけではなく実際の「行動」につなげるために、「karafuru AI(カラフルAI)」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
karafuru AI(カラフルAI)は、多様性のある組織づくりを継続的にサポートする対話型AIツールです。従業員それぞれのアンコンシャスバイアスのパターンを見える化し、個人の意識や行動の変容を促すことで、組織のアンコンシャスバイアスを解消しやすくなります。この機会にぜひご相談ください。
関連リンク
karafuru AI
https://www.nttbizsol.jp/service/karafuru-ai/
karafuru AIに関するお問い合わせ
https://form.nttbizsol.jp/inquiry/karafuru-ai
あわせて読みたいナレッジ
関連製品
Bizナレッジキーワード検索
- カテゴリーから探す
- 快適なオフィスの実現
- 生産性向上
- 労働力不足の解消
- セキュリティー対策
- ビジネス拡大
- 環境・エネルギー対策