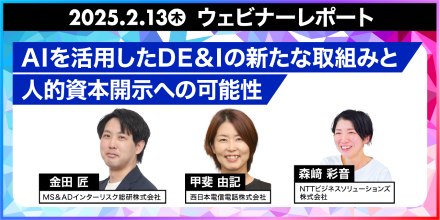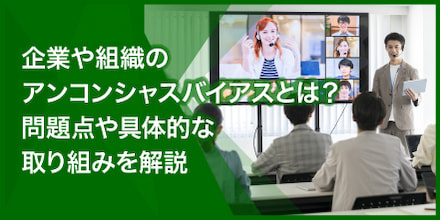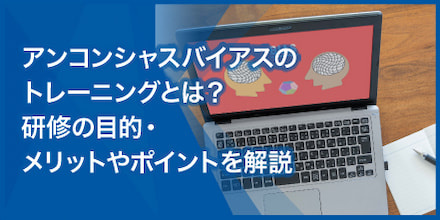ICTで経営課題の解決に役立つコラムを掲載
アンコンシャスバイアスの対策には「気づき」が重要!ポイントや対策を解説

「アンコンシャスバイアス」は、無意識下にある偏見や思い込みを指す用語です。アンコンシャスバイアスは職場における不公平や差別の原因となるため、社内でアンコンシャスバイアスと向き合う取り組みが欠かせません。
そのためには、従業員がアンコンシャスバイアスへの「気づき」を得ることが大切です。そこで本記事では、アンコンシャスバイアスの「気づき」について、メリットや重要なポイントを解説します。
アンコンシャスバイアスには「気づき」が大切
2010年代になり、企業で「アンコンシャスバイアス」が注目されることが増えました。無意識な偏見や思い込みから生じるアンコンシャスバイアスの対策には「気づき」が大切です。まずはアンコンシャスバイアスの気づきについて、次のポイントから解説します。
- アンコンシャスバイアスは誰にでも起こりうる
- アンコンシャスバイアスは差別や不公平につながる
- 「気づき」とは問題点や違和感を察知すること
アンコンシャスバイアスは誰にでも起こりうる
アンコンシャスバイアスとは、日本語で「無意識の偏見」を意味する用語です。アンコンシャスバイアスは過去の経験や日々接する情報、周囲の意見などさまざまなものから影響を受けて形成されるため、誰にでも起こりうる現象です。
例えば、血液型で相手の性格を想像したり、相手の出身地を聞いて「この人はお酒に強そう」と考えたりするなど、日常の些細なことでもアンコンシャスバイアスの影響があります。実際に、日本の労働組合におけるナショナルセンターである「日本労働組合総連合会」が行った調査によると、日常や職場において約95%の人がアンコンシャスバイアスの存在を認識しているという結果が出ているのです。
アンコンシャスバイアスは差別や不公平につながる
アンコンシャスバイアスは、時と場合によって差別や不公平につながることがあり、さまざまな企業や職場でもハラスメントなど身近な問題となっています。私たちには、年齢・性別・国籍・人種・性的指向・価値観などさまざまな属性がありますが、それらは業務パフォーマンスや成果には関係しないことが多いです。
しかし実際には、「この人はまだ若いからリーダーには向かない」「この人は外国人だから日本のビジネス文化を理解していないかもしれない」など、アンコンシャスバイアスによる決めつけが影響を及ぼすことがあります。アンコンシャスバイアスにより、本来実力を発揮できる人が活躍できなかったり、教育やサポートが必要な人が支援を受けられなかったりすることが問題なのです。
「気づき」とは問題点や違和感を察知すること
「気づき」とは、問題点や違和感を察知することです。例えば、「男性の役割」「女性の役割」といった概念について考えてみましょう。
確かに両者は身体的な役割は異なりますが、業務の役割や得意分野、知識・スキルなどは性別ではなく個々人の特性であり、属性によって判断されるべきものではありません。こうした本質を理解することが「気づき」であり、アンコンシャスバイアスと向き合うためには欠かせない要素です。
アンコンシャスバイアスへの「気づき」のメリット
アンコンシャスバイアスへの「気づき」を従業員に習慣づけることで、次のようなメリットが得られると考えられます。
- 職場の風通しが良くなる
- ハラスメントの防止につながる
- 人材を有効活用できるようになる
- パフォーマンスや生産性が向上する
- 離職率が低下して人材が定着する
- 企業イメージの向上につながる
職場の風通しが良くなる
従業員がアンコンシャスバイアスへの気づきを得ることで、職場のさまざまな場面における偏見・先入観や決めつけなどが減ります。これにより、職場のコミュニケーションや意見交換などの透明性が高くなり、アイデアを出しやすくなります。その結果、職場の風通しが良くなり、個々が主体性をもって働きやすくなるのです。
ハラスメントの防止につながる
セクハラやパワハラに代表される「ハラスメント」は、行為者に悪意がないケースも少なくありません。これは自分を中心に考えてしまう視野の狭さが原因です。アンコンシャスバイアスへの気づきを従業員に得てもらうことで、「もしかしたら不快感を与えてしまうかもしれない」と相手に配慮できるようになり、ハラスメントを未然に防ぎやすくなります。
人材を有効活用できるようになる
アンコンシャスバイアスの大きな問題点は、人材活用を適切に行いづらくなることです。アンコンシャスバイアスによる偏見や思い込みにより、人事評価や人材配置が適切にできなくなるからです。アンコンシャスバイアスへの気づきを得てもらうことで、従業員の能力やスキルを適切に評価して、相応しいポジションへの割り当てができるようになります。
パフォーマンスや生産性が向上する
アンコンシャスバイアスへの気づきを促すことは、職場のパフォーマンスや生産性の向上にも寄与します。ビジネスの成果を高めるためには、その場に応じた判断や洞察が欠かせません。アンコンシャスバイアスへの気づきを得た職場では、従業員が偏見なしで互いを尊重し合い、適切な情報共有や状況判断ができるため、誤解やミスを防ぎながら効率的に成果を出せます。
離職率が低下して人材が定着する
職場でハラスメントに向き合うことで、社内の風通しが良くなってハラスメントを予防でき、人事評価や人材配置の最適化が進みます。その結果、従業員にとって「働きやすい職場」を構築しやすくなります。満足できる環境であれば、離職を考える従業員が減るため、人材定着率が向上するのです。
企業イメージの向上につながる
近年では、企業や組織の「働く環境」への注目度が高まっており、それが好ましくない企業は社会や消費者からのイメージが低下してしまいます。アンコンシャスバイアスに向き合って適切に対処することで、前向きな組織の姿勢をアピールすることができます。結果的に求職者からのイメージも良くなり、組織の採用力も高まるでしょう。
アンコンシャスバイアスへの「気づき」を得る方法
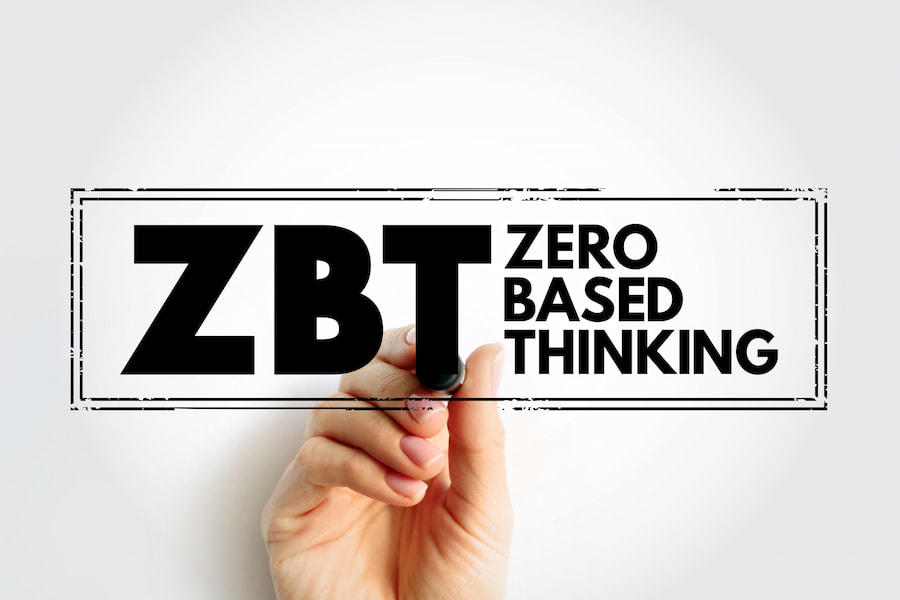
職場におけるアンコンシャスバイアスに向き合うために、次のようなポイントを意識して、従業員に気づきを得てもらうことが大切です。
- 自身のバイアスの傾向を理解する
- 自身と真逆の立場の視点を持つ
- 普段から情報のソースを重視する
- 「ゼロベース思考」を習慣づける
- 社内で継続的に研修を実施する
自身のバイアスの傾向を理解する
アンコンシャスバイアスには、次のようにさまざまなパターンが存在します。
| 正常性バイアス | 異常事態を「正常」と認識して平静を保とうとする |
|---|---|
| 確証バイアス | 自分に都合の良い情報に注目し、それ以外の情報を見落とす |
| ステレオタイプバイアス | 性別・人種・職業などの属性への先入観で他者を判断する |
| アインシュテルング効果 | 経験則による考え方や視点に固執してほかの可能性を無視する |
| ハロー効果 | ある対象の評価時に、目立つ要素に引きずられて評価が偏る |
| 権威バイアス | 権威のある人の意見や情報をすべて正しいと盲信してしまう |
| 慈悲的差別 | 立場が弱いと思う相手に対し、必要以上の配慮や気遣いをする |
| インポスター症候群 | 自身の実績や実力を信じることができず過小評価してしまう |
これらのバイアスパターンを知り、自身のアンコンシャスバイアスのどのような傾向があるかを理解することで、職場における偏見に対処しやすくなります。なお、アンコンシャスバイアスの具体例については、次の記事も合わせてご参照ください。
あわせて読みたい関連記事
自身と真逆の立場の視点を持つ
我々は程度の差はあれど、自分の立場で物事を考えて行動する傾向があります。前述したように、アンコンシャスバイアスは自身の経験や日常で得る情報などから生じますが、それは言い換えれば自分本位の視点が原因になるということです。
しかし実際には、役職やバックグラウンド・属性など人それぞれ立場が異なり、それにより物事の見方や言動が異なるのは当然のことです。ここに気づくことで、相手の立場に立ってアンコンシャスバイアスを解消しやすくなるでしょう。
普段から情報のソースを重視する
アンコンシャスバイアスは、日常で得る情報やニュースの偏りなどからも生じます。有名な企業や人が発信する情報であっても、発信者の主観が入ることはよくあるため、何事も妄信してしまわないように注意が必要です。前述した「権威バイアス」や「確証バイアス」の影響は特に受けやすいため、信じる前に立ち止まって疑ってみるようにしましょう。
「ゼロベース思考」を習慣づける
アンコンシャスバイアスに気づくためには、先入観に左右されない思考法を身に付けることも大切です。特に「ゼロベース思考」は、ゼロの状態から物事を考える思考法であり、前提条件を見直して公平な視点から見ることができます。
既存ルールや常識は、合理的な裏付けがないにも関わらず広く受け入れられていることがあり、それが「こうあるべき」「これで当然」というアンコンシャスバイアスにつながります。ゼロベース思考を身に付けることで、自身の思考の偏りや偏見に気づきやすくなるのです。
社内で継続的に研修を実施する
社内でアンコンシャスバイアス研修を継続的に実施することで、従業員の固定観念への気づきのきっかけとなります。ただし、従業員に研修を実施したとしても、それが「行動変容」につながらなければ、アンコンシャスバイアスは解消できません。
そのため知識のインプットだけではなく、アウトプットの機会も設けたトレーニングを行うことが理想的です。例えば対話型の研修を行うことで、他者のフィードバックを交えながら、自身のアンコンシャスバイアスへの気づきが得られます。そのための有効なツールとして、AIとの対話で自身のバイアスパターンを見える化できるトレーニングツールもあるため、ぜひ導入を検討してみましょう。
アンコンシャスバイアスへの気づきの実現には「karafuru AI(カラフルAI)」がおすすめ!

アンコンシャスバイアスは誰にでも起こりうる現象ですが、自覚しづらいため「気づき」を得られるような研修を実施することが大切です。特に対話型のトレーニングは、自身のバイアスの傾向を理解し、広い視野を身に付けるために役立ちます。
組織のアンコンシャスバイアスと向き合うための施策の一環として、「karafuru AI(カラフルAI)」の導入がおすすめです。karafuru AI(カラフルAI)は、多様性のある組織づくりを継続的にサポートする対話型AIツールです。今回解説したアンコンシャスバイアスを見える化し、個人の思考の偏りや偏見への「気づき」を実現し、意識や行動の変容を促しやすくなります。この機会にぜひご相談ください。
関連リンク
karafuru AI
https://www.nttbizsol.jp/service/karafuru-ai/
karafuru AIに関するお問い合わせ
https://form.nttbizsol.jp/inquiry/karafuru-ai
あわせて読みたいナレッジ
関連製品
Bizナレッジキーワード検索
- カテゴリーから探す
- 快適なオフィスの実現
- 生産性向上
- 労働力不足の解消
- セキュリティー対策
- ビジネス拡大
- 環境・エネルギー対策