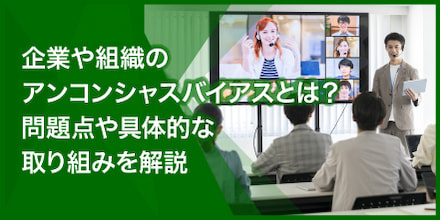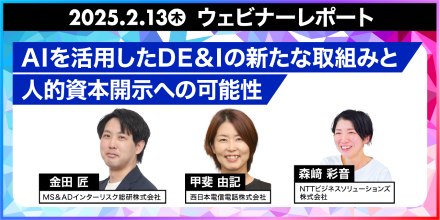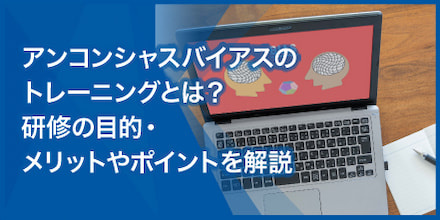ICTで経営課題の解決に役立つコラムを掲載
アンコンシャスバイアスとは?具体例や組織への悪影響・対処法を解説

アンコンシャスバイアスとは、無意識な偏見や思い込みを意味する概念です。アンコンシャスバイアスは不公平や差別などの原因になるため、職場のアンコンシャスバイアスと向き合って適切な対策を行う必要があります。
しかし、具体的にどんなものがアンコンシャスバイアスに該当するか、分からないこともあるでしょう。そこで本記事では、アンコンシャスバイアスの種類や、職場における悪影響の具体例について解説します。
アンコンシャスバイアスとは
アンコンシャスバイアスについて、まずは次のポイントから解説します。
- 無意識な偏見や思い込みを意味する用語
- アンコンシャスバイアスは誰もが有する
- アンコンシャスバイアスが職場へ与える影響は大きい
無意識な偏見や思い込みを意味する用語
アンコンシャスバイアスとは、無意識の偏見や思い込み、つまり自分自身では気付いていない「物事の見方・捉え方の偏り」を意味する用語です。
英語の「unconscious(無自覚)」と「bias(偏見)」を組み合わせた造語で、近年注目が高まっています。アンコンシャスバイアスは、過去の経験や知識、日々接する情報や周囲の意見など、さまざまなものから影響を受けて形成されていきます。
アンコンシャスバイアスは誰もが有する
程度の差こそあれど、アンコンシャスバイアスは誰もが有するものです。例えば、「消防士」「看護師」といった職種を聞いたとき、どのような人をイメージするでしょうか。ほとんどの人は、「消防士はこんな人」「看護師はこんな人」のように、特定のイメージを思い浮かべがちです。
実際に令和4年に内閣府男⼥共同参画局が発表した調査結果では、「男性は仕事をして家計を⽀えるべきだ」「⼥性は感情的になりやすい」など、性別に基づくアンコンシャスバイアスの存在が指摘されています。
アンコンシャスバイアスが職場へ与える影響は大きい
アンコンシャスバイアスは、企業に次のような悪影響をもたらすため、適切な対策を行う必要があります。
- 採用や人事評価で不適切な判断が行われる
- 組織全体のパフォーマンスが低下する
- 多様なアイデアが生まれなくなる
- 離職率が増加して人材が定着しなくなる
特に大きな問題が、人材の育成・活用・評価などが適切に行われなくなることです。自身の成果や努力が評価されなければ、従業員のエンゲージメントやパフォーマンスは低下します。また、組織における人財の多様性が喪失されることでアイデアも画一的になり、新たな価値やビジネスの創出が困難となるでしょう。
アンコンシャスバイアスの種類
アンコンシャスバイアスには、次のような種類のものがあります。それぞれの特徴について見ていきましょう。
- 正常性バイアス
- 確証バイアス
- ステレオタイプバイアス
- アインシュテルング効果
- ハロー効果
- 権威バイアス
- 慈悲的差別
- インポスター症候群
正常性バイアス
「正常性バイアス」とは、自身が危機的状況にあるにも関わらず、都合の悪い情報を無視あるいは過小評価することです。例えば、自社の業績が悪化しているというデータが出たとき、「まだ大丈夫だ」「うちが倒産するわけない」と判断するなどです。正常性バイアスがあることで、対応が後手に回って手遅れになるケースが増えます。
確証バイアス
「確証バイアス」とは、自身の信念・価値観・仮説などの「正しさ」を支持できる情報を集めようとして、それ以外を無視することです。
例えば、あるプロジェクトの反対派がリスクやデメリットばかりを探して、「このプロジェクトは危険だ」と主張するなどです。確証バイアスの作用により、客観的・科学的な事実が歪められ、適切な意思決定の妨げになるケースが増えます。
ステレオタイプバイアス
「ステレオタイプバイアス」とは、性別・年齢・国籍・職業などの属性によって、固定観念に基づき判断することです。
例えば、「あの人は外国人だから、自己主張が強くてマイペースだろう」と思い込むなどです。ステレオタイプバイアスにより、事実ではなく偏見で判断することが増えるため、組織メンバーの不適切な言動が問題になるかもしれません。
アインシュテルング効果
「アインシュテルング効果」とは、これまでの経験で慣れ親しんだ考え方やプロセスに固執し、ほかの選択肢を排除してしまうことです。例えば、イレギュラー発生時でも従来のマニュアルどおりの対応から脱却できないなどです。アインシュテルング効果により、新たな意見やアイデアが受け入れられない「風通しの悪い」組織風土が根付いてしまいます。
ハロー効果
「ハロー効果」とは、何かを評価するときに、その目立つ特徴に意識が引っ張られて、すべての評価が影響されてしまうことです。例えば採用面接のときに、学歴が高い候補者を「仕事ができるに違いない」と判断してしまうなどです。ハロー効果により、対象者の本質を見極めることが難しくなり、不適切な評価や育成の原因となります。
権威バイアス
「権威バイアス」とは、権威のある人や専門家の言動について深く考えず、「すべて正しい」と思い込んでしまうことです。例えば、上司の言うことをすべて正しいと思い込み、疑うことなく従ってしまうなどです。権威バイアスが蔓延している職場では、上長に対して意見しづらいため風通しが悪く、正しい判断ができなくなる傾向があります。
慈悲的差別
「慈悲的差別」とは、少数派や立場が弱いと思われる相手に対して、必要以上の配慮や気遣いをしてしまうことです。例えば、本人がキャリアを望んでいるにも関わらず、子育て中の女性に割り当てるタスクを減らすなどです。慈悲的差別により、従業員が求める成長の機会を奪ったり、かえって不快感を与えてしまったりします。
インポスター症候群
「インポスター症候群」とは、自身の能力・スキルや実績を過小評価し、自己不信感に陥ってしまうことです。例えば、上司がチームのリーダーに推薦してくれたものの、「どうせ上手くできない」と考えて断ってしまうなどです。インポスター症候群により、自信が持てない従業員が増え、人材育成や人材活用などに課題が生じやすくなります。
職場におけるアンコンシャスバイアスの具体例

職場におけるアンコンシャスバイアスの具体例について、次のパターンに分けて紹介します。
- 採用活動
- 人事評価
- 人材育成
- 人材活用
採用活動
採用活動におけるアンコンシャスバイアスの具体例として、次のようなものが挙げられます。
- 前職の企業規模で、求職者の知識やスキルを判断して、採用の可否を判断する
- 自身と同じ大学出身の人を優遇したり、自分と境遇や考え方が似ている人を採用したりする
- 「女性は総合職に向かない」と判断し、求職者を一般職として採用しようとする
求職者の本質を正しく評価できないため、自社が必要とする人材を獲得しづらくなります。
人事評価
人事評価におけるアンコンシャスバイアスの具体例として、次のようなものが挙げられます。
- 定時退社が多い部下を「勤勉さに欠ける」と判断し、人事評価を下げる
- 仕事の成果に影響しない年齢・性別・国籍・性的指向など、個人の属性を評価に含める
- 自分と気の合う部下であれば、たとえパフォーマンスが低くても高く評価する
従業員の人事評価が正しく行われなくなるため、従業員が不満を感じて離職者が増えやすくなります。
人材育成
人材育成におけるアンコンシャスバイアスの具体例として、次のようなものが挙げられます。
- 「女性は結婚・妊娠・出産で職場を離れやすい」という思い込みから、女性のキャリアアップをサポートしない
- 実際の業務パフォーマンスに関係なく、自身と同じ大学の出身者を優先的に育成する
従業員が希望するキャリアのサポートが得づらくなり、自社の人材の多様性が阻害されてしまいます。
人材活用
人材活用におけるアンコンシャスバイアスの具体例として、次のようなものが挙げられます。
- 「子育て中の女性に転勤は無理」という思い込みから、転勤がない異動しかさせない
- 性別や国籍が成果に影響しない業務であるにも関わらず、属性により昇進を決める
- 「まだ若いから難しいだろう」という理由で、パフォーマンスが高い若年の従業員を昇進させない
従業員の特性やスキルに合わせた人材活用ができないため、それぞれの知識・スキルを発揮しづらい職場になってしまいます。
アンコンシャスバイアスを解消するための対策法
アンコンシャスバイアスを解消するために、次のような対策法を実施してみましょう。
- 社内の実態をヒアリングして把握・可視化する
- 従業員に研修や対話会を実施して多様性への理解を促す
- 教育内容を「行動変容」につなげる
社内の実態をヒアリングして把握・可視化する
組織におけるアンコンシャスバイアスの現状を把握するために、ヒアリングやアンケートなどを行います。アンケート調査では、具体例を提示して当てはまるかどうかを回答してもらうことで、アンコンシャスバイアスの傾向を把握できます。実態をより詳細に把握するためには、話し合いの場を設けたうえで各従業員へヒアリングを行うといいでしょう。
従業員に研修や対話会を実施して多様性への理解を促す
現状を把握したあとは、座学やロールプレイングなどを交えて、アンコンシャスバイアスのトレーニングを行います。具体的には、まずは自身のバイアスと向き合ってもらったうえで、他者への配慮や広い視野などを学びます。
適切な研修やトレーニングを行うことで、従業員が多様性を尊重する組織風土を醸成できるでしょう。なお、アンコンシャスバイアスのトレーニングについては、次の記事も合わせてご参照ください。
あわせて読みたい関連記事
教育内容を「行動変容」につなげる
従業員にアンコンシャスバイアスのトレーニングを実施したとしても、それが「行動変容」につながらなければ、アンコンシャスバイアスは解消できません。アンコンシャスバイアスは自覚しづらいため、知識のインプットだけではなく、アウトプットの機会も設けたトレーニングを行うことが理想的です。
例えば対話型の研修を行うことで、他者のフィードバックを交えて自身のアンコンシャスバイアスへの気づきが得られるため、アンコンシャスバイアスへの理解がさらに深まります。そのための有効な手段として、AIとの対話を通じて自身のバイアスパターンを見える化でき、意識改革や行動変容につなげられるトレーニングツールもあるため、ぜひ導入を検討してみましょう。
アンコンシャスバイアスの対策には「karafuru AI(カラフルAI)」がおすすめ!

アンコンシャスバイアスは誰もが有する偏見や思い込みですが、職場においては採用活動・人事評価・人材育成・人材活用など、さまざまな場面で悪影響が出てしまいます。誰もが働きやすい職場をつくるために、アンコンシャスバイアスと向き合うための対策を行うことが大切です。
そのためには、従業員への教育だけではなく、実際の「行動」につなげることが大切です。そこで「karafuru AI(カラフルAI)」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。karafuru AI(カラフルAI)は、多様性のある組織づくりを継続的にサポートする対話型AIツールです。アンコンシャスバイアスを見える化し、個人の意識や行動の変容を促すことで、注目されることが増えた「DE&I」の推進にも役立ちます。この機会にぜひご相談ください。
関連リンク
karafuru AI
https://www.nttbizsol.jp/service/karafuru-ai/
karafuru AIに関するお問い合わせ
https://form.nttbizsol.jp/inquiry/karafuru-ai
あわせて読みたいナレッジ
関連製品
Bizナレッジキーワード検索
- カテゴリーから探す
- 快適なオフィスの実現
- 生産性向上
- 労働力不足の解消
- セキュリティー対策
- ビジネス拡大
- 環境・エネルギー対策