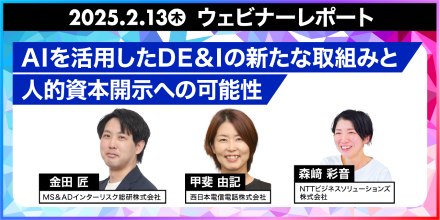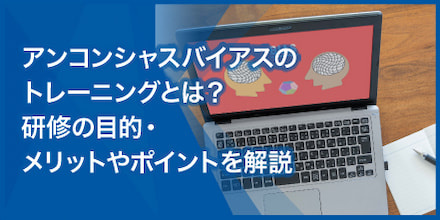ICTで経営課題の解決に役立つコラムを掲載
企業や組織のアンコンシャスバイアスとは?問題点や具体的な取り組みを解説

「アンコンシャスバイアス」とは、私たちが無意識のうちに抱えている偏見や思い込みのことです。アンコンシャスバイアスは、企業や自治体などの組織のマネジメントに悪影響を与えるリスクがあります。だからこそ、組織はアンコンシャスバイアスと向き合う必要があるのです。
しかし、具体的にどのような取り組みを行うべきか、分からないことも多いでしょう。そこで本記事では、企業・自治体がアンコンシャスバイアスに向き合うべき理由や、具体的な取り組み事例について解説します。
企業・組織のアンコンシャスバイアスが注目されている
2010年代頃より、企業で「アンコンシャスバイアス」が注目されることが増えました。日本の企業・自治体でも改善に向けた取り組みが加速しています。その理由や背景について、次のポイントから解説します。
- 無意識下で形成される偏見や思い込み
- アンコンシャスバイアスは誰にでもある
- よくあるアンコンシャスバイアスの例
無意識下で形成される偏見や思い込み
「アンコンシャスバイアス」とは、無意識のうちに形成されている偏見や思い込みを意味します。アンコンシャスバイアスは、過去に得た経験や知識が元となって形成されますが、自身で「気づき」を得るのは容易なことではありません。そのため、日常生活はもちろん業務におけるさまざまな場面で、アンコンシャスバイアスの影響を受ける可能性があるのです。
アンコンシャスバイアスは誰にでもある
アンコンシャスバイアスは決して特殊な現象ではなく、私たちの誰もが有している思考パターンです。例えば、医師や看護師という職業を聞いたとき、「医師は男性」「看護師は女性」と無意識にイメージする人は少なくないでしょう。
このように、ある職業や集団の名称を挙げたときに特定の属性を連想するのが、アンコンシャスバイアスの代表例です。そのほかにも、相手が自身と同じ知識や考えを持っている前提で話したり、相手の年齢や性別などによって接し方を変えたりすることも、アンコンシャスバイアスのひとつだといえます。
よくあるアンコンシャスバイアスの例
アンコンシャスバイアスの代表的な例として、次のようなものが挙げられます。
- この人は男性だから力仕事が得意なはず
- 子育て中の女性には泊りがけの出張は無理だろう
- 独身の人は結婚できなくて可哀想だと思う
- この人はまだ若いから職位は低いだろう
- 学歴が高い人は仕事もできるに決まっている
- 残業しない人は勤勉ではないから評価を下げるべきだ
- 女性は出産したら退職するのが当たり前だ
- あの人は自分と同じ大学出身だから優秀だろう
いずれも「~のはず」「当然~だろう」という思い込みや、決めつけによる思考パターンが特徴です。もちろんすべてが「悪意のある思考」とは限りませんが、こうした思い込みや偏見の積み重ねが、職場や業務に悪影響を与えかねないのです。
企業・組織でアンコンシャスバイアスに向き合う取り組みが必要な理由
アンコンシャスバイアスは、次のような悪影響を組織や個人に及ぼすため、アンコンシャスバイアスに向き合うための取り組みが必要です。
- ハラスメント行為が常態化してしまう
- 従業員のキャリアの阻害につながってしまう
- モチベーションの低下で業績が悪化する
- 多様性がなくイノベーションが生まれにくい
- 離職が増えて優秀な人材の流出につながる
- 企業やブランドのイメージが毀損される
ハラスメント行為が常態化してしまう
ハラスメントの種類には、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなどがあり、これらの多くにアンコンシャスバイアスが関係しています。アンコンシャスバイアスは誰にでも存在しますが、悪意のない言動が相手に「ハラスメント」と見なされるケースは決して珍しくありません。
例えば、上司が部下の負担を軽減するために性別に応じてタスク配分を変えたとき、部下は「負担軽減」ではなく「性差別」だと感じてしまうかもしれません。前述したように、アンコンシャスバイアスは自覚がないことが多いため、ハラスメントの常態化につながってしまうのです。
従業員のキャリアの阻害につながってしまう
アンコンシャスバイアスによる「決めつけ」により、従業員のキャリアが阻害されてしまうこともあります。例えば、年齢や性別によって業務内容を制限する職場では、従業員が理想のキャリアを歩めない可能性があります。その結果、適材適所の人材配置ができず、職場から多様性が失われてしまうでしょう。
モチベーションの低下で業績が悪化する
ハラスメントが常態化していたり、自由なキャリア選択ができなかったりする職場では、当然ながら従業員の「働く意欲」が失われてしまいます。従業員のモチベーションとパフォーマンスには密接な関係があるため、メンバーの意欲が削がれた組織の業績が悪化するのは当然の結果です。
多様性がなくイノベーションが生まれにくい
アンコンシャスバイアスには、異常の発生時にそれを正常なことだと見なす「正常性バイアス」や、都合の良い情報だけを集める「確証バイアス」があります。つまり、企業や自治体などが抱えている課題が見過ごされ、必要な対策が行われなくなるということです。
また、アンコンシャスバイアスが蔓延している職場では、従業員の思考に多様性がなく、現状維持の精神が根付いている傾向があります。そのため、新たな価値やイノベーションの創出も困難なのです。
離職が増えて優秀な人材の流出につながる
アンコンシャスバイアスは離職者の増加にもつながります。前述した悪影響によって従業員のモチベーションは低下し、より働きやすい環境を求めるようになるからです。「不適切な人事評価」は、従業員が特に組織への不満を感じやすい要素です。
アンコンシャスバイアスを自覚せずに人事評価を行うと、対象者の評価に偏りが出て、成果や努力を適切に反映できなくなります。これにより競合他社に人材が流出しやすくなりますが、人手不足が深刻化している昨今では、自社ビジネスの持続可能性に大きな悪影響となるでしょう。
企業やブランドのイメージが毀損される
アンコンシャスバイアスへの対応は、企業や自治体の姿勢を表明することでもあります。近年では、社会や消費者に組織の姿勢が問われるケースが増えており、不適切な対応は企業・ブランドイメージの毀損につながりかねません。
一度失われた信頼は、容易に回復できるものではないでしょう。「社会への責任を果たす組織である」というメッセージを発信するためには、アンコンシャスバイアスと適切に向き合い、不平等や不公正を是正する必要があるのです。
企業・組織のアンコンシャスバイアスへの取り組みポイント

企業や自治体がアンコンシャスバイアスを改善するためには、次のようなポイントを意識して取り組みを行うことが大切です。
- 従業員に「気づき」を得てもらう
- 体験型研修の導入で理解を深める
- 多様な従業員を意思決定の場に迎える
- 心理的安全性の高い職場環境をつくる
- 研修を実施して多様性を醸成する
従業員に「気づき」を得てもらう
企業・自治体のアンコンシャスバイアスを取り除くために、まずは従業員にアンコンシャスバイアスへの「気づき」を得てもらいましょう。
従業員が自身のアンコンシャスバイアスを把握したあとは、「現在の社会情勢に適合するか」「相手がどのように感じるか」についてディスカッションを行います。なお、アンコンシャスバイアスへの気づきについては、次の記事も合わせてご参照ください。
あわせて読みたい関連記事
体験型研修の導入で理解を深める
企業・自治体のアンコンシャスバイアスと本質的に向き合うためには、ロールプレイやディスカッションなどによる「体験型」の研修も欠かせません。
例えば、社会的に問題視された広告や動画などを題材として、「何が問題か」「どうすれば良かったか」などの観点で話し合うことで、より深い気づきや理解が得られます。それを普段の業務の様子と絡めることで、社内のアンコンシャスバイアスを本質的に解消しやすくなるでしょう。
多様な従業員を意思決定の場に迎える
社内のアンコンシャスバイアスを解消するためには、多様な意見を持つ従業員を意思決定の場に加えることも大切です。同じ方向性や価値観がある人だけで固めると、意思決定はスムーズに進みやすいですが、画一的な意見やアイデアしか出なくなります。また、異なる意見がある従業員が発言しづらくなるため、社内の風通しの悪化にもつながるでしょう。
心理的安全性の高い職場環境をつくる
アンコンシャスバイアスが存在する職場では、「偏見」「思い込み」「決めつけ」などが増えるため、従業員がそれぞれの意見や考えを表明しづらい組織風土が生まれます。言い換えれば、「心理的安全性」が低い組織になるということです。
心理的安全性とは、意見や考えを表明しやすいかどうかを示す指標です。心理的安全性が高い職場をつくるためには、互いを尊重し合えるような組織風土を作る必要があります。つまり、心理的安全性を高める過程で、アンコンシャスバイアスとも向き合えるようになるということです。
研修を実施して多様性を醸成する
従業員に適切な研修を行い、それが「行動変容」につながらなければ、職場のアンコンシャスバイアスは解消できません。しかし、アンコンシャスバイアスは自身で自覚しづらいため、知識のインプットだけではなく、アウトプットの機会も設けたトレーニングを行うことが理想的です。
例えば、対話型の研修を実施すると、他者のフィードバックを受けながら自身のアンコンシャスバイアスに気づきやすくなり、理解が深まります。そのための効果的な手段として、AIとの対話を通じて自身のバイアスパターンを見える化でき、意識改革や行動変容につなげられるトレーニングツールもあるため、ぜひ導入を検討してみましょう。
企業・組織のアンコンシャスバイアスを解消する取り組みの事例
組織がアンコンシャスバイアスと向き合うための施策には、さまざまな種類のものがあります。そのひとつとして、対話型AIを活用したアンコンシャスバイアストレーニングツール「karafuru AI(カラフルAI)」がおすすめです。ここでは、karafuru AI(カラフルAI)の導入事例を3件ご紹介します。
- 多様な従業員が働きやすい職場を構築
- 人事担当者に「Equity」の考え方を浸透
- 新任管理者向け研修のアウトプットに活用
多様な従業員が働きやすい職場を構築
情報通信業のA社では、女性従業員の割合が比較的高く、年齢層・経験・雇用区分も多様です。しかし、同社のエンゲージメント調査では「DE&I」に関する評価が低いことが課題でした。つまり、多様な従業員が働きやすい職場ではなかったのです。
そこで同社はkarafuru AI(カラフルAI)を導入し、全管理者を対象としてアンコンシャスバイアスのトレーニングを実施しました。「なぜDE&Iが重要か」「なぜアンコンシャスバイアスのトレーニングをするか」を説明し、理解を深めてもらいました。その結果、従業員にとって働きやすい職場環境の醸成が進んでいます。
人事担当者に「Equity」の考え方を浸透
商社のB社では、「DE&I」の重要性は従業員に理解されていました。しかし、人事担当者がアンコンシャスバイアスから脱却しきれないため、公正公平な人事評価ができないことが課題でした。例えば、雇用形態や性別などに対する先入観があり、本質を見ずに判断してしまうなどです。
そこで同社は、「アンコンシャスバイアスを可視化することで克服できるのではないか」と考え、karafuru AI(カラフルAI) を導入しました。まずは自身のアンコンシャスバイアスに気付いてもらい、AIとの対話でトレーニングを行うという流れで研修を行うようにしました。その結果、人事担当者のアンコンシャスバイアスへの理解が深まり、人事評価制度の改善が進んでいます。
新任管理者向け研修のアウトプットに活用
金融業のC社では、社内の人事事案の9割がアンコンシャスバイアスに起因していました。そこで新任管理者研修で、アンコンシャスバイアスのトレーニングを実施しましたが、十分な効果が得られませんでした。
そこで同社では、アウトプットの機会で学びを深めるために、karafuru AI(カラフルAI)を導入し、グループワークと個人ワークを組み合わせたトレーニングを実施しました。知識のインプットだけではなくアウトプットも交えることで、担当者が自身のアンコンシャスバイアスに気づきやすくなり、改善に向けた取り組みが進んでいます。
アンコンシャスバイアスの解消には「karafuru AI(カラフルAI)」がおすすめ!

企業・組織のアンコンシャスバイアスは、ハラスメント行為の常態化や、従業員のキャリアの阻害などにつながります。さまざまなバックグラウンドがある従業員が活躍できる職場をつくるためには、アンコンシャスバイアスと向き合う取り組みを実施することが大切です。
そのためには、知識をインプットする教育だけではなく、アウトプットの機会も設けてトレーニングを行い、実際の「行動」につなげる必要があります。そこで「karafuru AI(カラフルAI)」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
karafuru AI(カラフルAI)は、多様性のある組織づくりを継続的にサポートする対話型AIツールです。今回解説したアンコンシャスバイアスを見える化し、個人の意識や行動の変容を促すことで、組織のアンコンシャスバイアス解消の取り組みに役立ちます。この機会にぜひご相談ください。
関連リンク
karafuru AI
https://www.nttbizsol.jp/service/karafuru-ai/
karafuru AIに関するお問い合わせ
https://form.nttbizsol.jp/inquiry/karafuru-ai
あわせて読みたいナレッジ
関連製品
Bizナレッジキーワード検索
- カテゴリーから探す
- 快適なオフィスの実現
- 生産性向上
- 労働力不足の解消
- セキュリティー対策
- ビジネス拡大
- 環境・エネルギー対策